2025.12.24
ReGeneralインタビュー、セッションの様子を更新しました
2025年度 厚生労働省補助事業採択
総合医育成プログラムは、
「総合医リカレント実践事業 ReGeneral」
として全日本病院協会と
日本プライマリ・ケア連合学会が
運営するオンライン教育プログラムです。
(事業概要)
2025.12.24
ReGeneralインタビュー、セッションの様子を更新しました
これまでに培った専門性と臨床経験に
「総合診療能力」を加え、
新たなキャリアを築きませんか?
少子高齢化と人口減少が進むこれからの時代、医師にはより多様な患者を幅広く診療できるスキルが求められています。
総合医育成プログラムは、専門領域での経験を持つ医師が、総合医としても活躍できる実践的な能力を効率的に習得できるよう設計されたオンラインのコースです。
本プログラムは、2019年の開始から7期目を迎え、2025年に厚生労働省「総合的な診療能力を持つ医師養成のためのリカレント教育推進事業」に採択されました。
同年度から、同期型・非同期型学習を組み合わせることで研修にかかる時間を大幅に削減するとともに、厚生労働省の助成を受けて受講料を約50%引き下げ、従来よりもさらに受講しやすくなりました。
本プログラムを活用し、今後の社会ニーズに応じる診療能力を獲得し、ミドルキャリアからの新たな活躍の場を広げてください。


公益社団法人 全日本病院協会 会長/
社会医療法人財団菫仙会 恵寿総合病院 理事長
少子高齢化や人口減少、さらには医師の地域偏在により、専門医偏重では持続可能な医療提供体制や地域包括ケアの実現が困難となっています。こうした中で、急性期から在宅まで横断的に対応し、多職種連携を牽引できる「総合医」の育成は、地域医療を守る鍵となる重要な課題です。全日本病院協会では、専門医制度とは異なるリカレント教育の一環として、日本プライマリ・ケア連合学会と協力し、系統的な教育プログラムを整備・提供しています。地域と病院が抱える課題の解決に向けて、本プログラムにぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
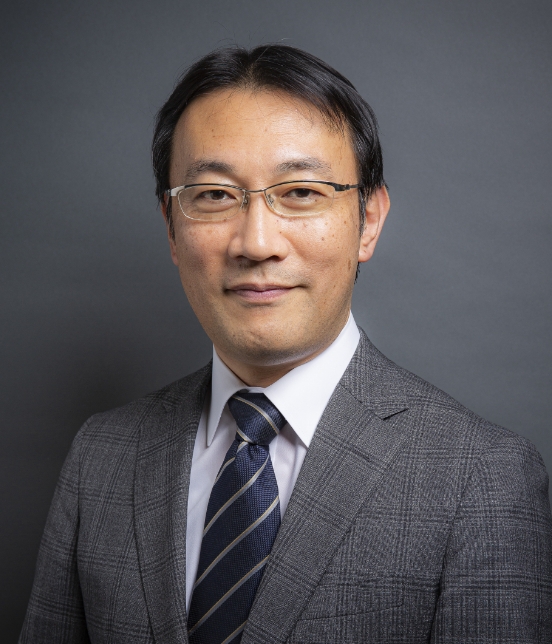
一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 理事長/
医療法人 北海道家庭医療学センター 理事長
この度、全日本病院協会と当学会が連携して運営してきた総合診療リカレント事業が厚生労働省事業に採択されたことを大変嬉しく思っております。学会では数十年間、現場の実地医家を支援すべく生涯教育を提供してきましたが、本事業ではそのノウハウを惜しみなくつぎ込み、大変質の高いコースが完成したと自負しております。総合診療を学んだ医師が地域でその能力を発揮することは、高齢化と人口減少が進む日本の社会にとって欠かせません。多くの方のご参加を心よりお待ちしております。
Feature
01
e-learningと土日中心のライブ研修
(オンライン形式)で受講可能
Feature
02
現場を熟知し多くの教育ノウハウを持つ
日本プライマリ・ケア連合学会が検討を重ねて開発
Feature
03
これまでの専門医としての経験をベースに、プライマリ・
ケアの実践的なスキルを修得して診療の幅を広げる
Feature
04
修了者は筆記試験免除で日本プライマリ・ケア連合学会認定医/全日本病院協会認定総合医を取得可能

日本プライマリ・ケア連合学会 副理事長/
筑波大学附属病院 副病院長・総合診療科長
前野 哲博
この研修は、すでに自分の専門領域に関する経験をもつ医師が、その経験を生かしつつ、プライマリ・ケアにキャリアを広げることを支援するために開発されました。
プログラムは、自分の苦手な診療領域の底上げを図ることができる診療実践コースと、地域包括ケアシステムのなかでチームを作りあげ、円滑に運営していくために、組織人として必要なスキルであるノンテクニカルスキルコースから構成されています。
研修は完全オンライン形式で実施されるため、全国どこからでも、現在の職場を離れることなく参加可能です。オンライン形式だと受動的な「座学」になりがちですが、本プログラムでは、非同期型学習(eラーニング)と同期型学習(ライブ研修)を組み合わせた能動学修を取り入れることにより、実践的なスキルを効率的に修得できます。
研修のコーディネートは、各領域の専門医と、地域医療の実践および教育の現場を知りつくした総合診療のエキスパートで構成される日本プライマリ・ケア連合学会のプロジェクトチームが共同で行っています。そのコンセプトは「プライマリ・ケアの現場で一歩踏み出せること」です。取り扱う内容は、高度な専門知識や技術ではなく「非専門医にとって現場で必要なスキル」に大胆に絞り込むとともに、教科書を読んだだけではわからない「まさにここが知りたかった!」というポイントが満載です。ぜひ、多くの方々の参加をお待ちしています。
この研修は、すでに自分の専門領域に関する経験をもつ医師が、その経験を生かしつつ、プライマリ・ケアにキャリアを広げることを支援するために開発されました。
プログラムは、自分の苦手な診療領域の底上げを図ることができる診療実践コースと、地域包括ケアシステムのなかでチームを作りあげ、円滑に運営していくために、組織人として必要なスキルであるノンテクニカルスキルコースから構成されています。
研修は完全オンライン形式で実施されるため、全国どこからでも、現在の職場を離れることなく参加可能です。オンライン形式だと受動的な「座学」になりがちですが、本プログラムでは、非同期型学習(eラーニング)と同期型学習(ライブ研修)を組み合わせた能動学修を取り入れることにより、実践的なスキルを効率的に修得できます。
研修のコーディネートは、各領域の専門医と、地域医療の実践および教育の現場を知りつくした総合診療のエキスパートで構成される日本プライマリ・ケア連合学会のプロジェクトチームが共同で行っています。そのコンセプトは「プライマリ・ケアの現場で一歩踏み出せること」です。取り扱う内容は、高度な専門知識や技術ではなく「非専門医にとって現場で必要なスキル」に大胆に絞り込むとともに、教科書を読んだだけではわからない「まさにここが知りたかった!」というポイントが満載です。ぜひ、多くの方々の参加をお待ちしています。
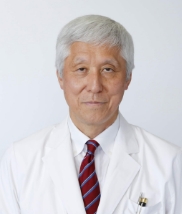
全日本病院協会 常任理事/
社会医療法人春回会 井上病院 理事長
井上 健一郎
今日の医療は、多疾疾患や認知症を抱える高齢患者の増加により一層複雑になっています。地域には医療と介護の課題を同時に抱えるマルチプロブレムの高齢者が増え、院内外の多様なチームによる医療が不可欠です。その中で、専門外だからと切り捨てずに患者を受け止める姿勢を持つ総合医が強く求められています。
総合医は専門医療の隙間を埋め、地域全体の医療を統合する存在です。総合医育成プログラムは、ベテランの臓器別専門家として活躍してきた医師が、自院で診療を続けながら学べる仕組みです。幅広い臨床スキルに加え、チームを率いるマネジメント力やコーチング力も養えます。受講者が外来・病棟・在宅などのこれまで診ることがなかった領域の診療能力を補強することで、病院全体の診療体制の安定化と人材の厚みに直結します。
概ね2年間の受講の前後で実施している受講者アンケート調査において、これまで専門領域の関係で診療することのなかった「抗凝固療法」や「骨折初期対応」、「軽症うつ病の管理」をできるようになったなど、診療の幅が確実に拡大した方が多数おられます。本プログラムへの参加は、医師個人の成長のみならず、病院経営と地域医療を守るための重要な一歩になると確信しています。
今日の医療は、多疾疾患や認知症を抱える高齢患者の増加により一層複雑になっています。地域には医療と介護の課題を同時に抱えるマルチプロブレムの高齢者が増え、院内外の多様なチームによる医療が不可欠です。その中で、専門外だからと切り捨てずに患者を受け止める姿勢を持つ総合医が強く求められています。総合医は専門医療の隙間を埋め、地域全体の医療を統合する存在です。総合医育成プログラムは、ベテランの臓器別専門家として活躍してきた医師が、自院で診療を続けながら学べる仕組みです。幅広い臨床スキルに加え、チームを率いるマネジメント力やコーチング力も養えます。受講者が外来・病棟・在宅などのこれまで診ることがなかった領域の診療能力を補強することで、病院全体の診療体制の安定化と人材の厚みに直結します。
概ね2年間の受講の前後で実施している受講者アンケート調査において、これまで専門領域の関係で診療することのなかった「抗凝固療法」や「骨折初期対応」、「軽症うつ病の管理」をできるようになったなど、診療の幅が確実に拡大した方が多数おられます。本プログラムへの参加は、医師個人の成長のみならず、病院経営と地域医療を守るための重要な一歩になると確信しています。

医療法人外海弘仁会 雪浦ひうらクリニック院長/法人理事
廣田 康宏 先生(2023年度修了)
発足当初から知っていた研修会ですが、会場に出向く必要があり参加をためらっていました。コロナ禍でweb形式となり迷わず申し込み、大変充実した学びを得ました。私の専門は整形外科とリハビリですが、地域包括ケアを学んだのを契機に、地元で全人的医療を提供する活動を平成20年から続けており、この先百年もつ体制の構築を自らのテーマとしています。本プログラムでは、診療実践コースにおいては各臓器別疾患への対応から、感染症、認知症に至るまで、幅広い学びを得ました。そうした臨床知識に留まらず、ノンテクニカルスキルコースでは、チームビルディングや職員教育、多職種連携に関わるノウハウを学びました。新型コロナ蔓延期に私が関わる特養やグループホームでクラスターを経験したものの、死亡者ゼロを継続できたのは、本プログラムを受講し自身の実践に取り入れた成果だと思っています。

社会医療法人協和会
加納総合病院
板垣 成彦 先生(2025年度受講中)
私は大阪府郊外の中規模病院に勤務する救急医で、総合診療医的な部分も担っています。
このプログラムのことは日本プライマリ・ケア連合学会を介して知りました。診療実践コースとノンテクニカルスキルコースの2コースからなり、前者では講義とワーキングによって、幅広い分野にわたる国家試験以来の体系だった学習が可能です。後者では、コーチングや認知スタイルなど、直接の医療知識ではありませんが、現場で役立つ技能を習得しています。
いずれも臨床現場を意識した展開をしてくださるため、日常診療で自分の行動が変容してきているという実感があります。また、さまざまな立場の、似たような悩みや思いを持っておられる医師の方々と知り合えるのは貴重な時間であり、経験であると思っています。

京都田辺中央病院
総合診療科・循環器内科
西尾 学 先生(2025年度受講中)
臓器別診療科での専門的キャリアだけでは学べない様々な診療科のエッセンスや、医療面接や研修指導、快適な職場実現のためのノンテクニカルスキルを、自宅や職場で居ながらに学べるとても優れたプログラムで、内容も毎回とても楽しいです。受講もとても融通が利くもので、すきま時間や当直の空き時間に少しずつe-ラーニングと小テストを行って無理なく各診療科・領域についてまず理解することができます。同期型学習でそれを強化することで、その項目についてまったく知らない、もしくは忘れていても確実に習得を積むことができます。さらに同期型学習では全国の総合医を学んでいる先生方と交流しながら学ぶことがとても楽しい時間となっております。当直中の楽しみがひとつ増える上に、総合医になれるこのプログラムを全国の総合診療を行いたい先生方におすすめします。